高座数と木戸銭の今むかし
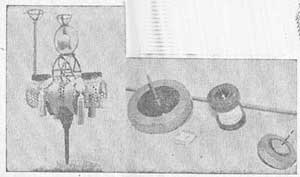 寄席の組織というか、習慣というかも昔と今とではずいぶん変りましたね。もっとも明治
末期は木戸が六銭くらいだったのが十銭になり…いつごろまで続いたか十銭という時
代はだいぶ長く続きましたが、それが大正になって十三銭になり…もっとも二流の席
は八銭、佐竹ツ原の久米亭なんか大正になっても五銭でやってましたが、それがどうです、
今では百五十円、二百円なんてんですからね、夢ですよ。
寄席の組織というか、習慣というかも昔と今とではずいぶん変りましたね。もっとも明治
末期は木戸が六銭くらいだったのが十銭になり…いつごろまで続いたか十銭という時
代はだいぶ長く続きましたが、それが大正になって十三銭になり…もっとも二流の席
は八銭、佐竹ツ原の久米亭なんか大正になっても五銭でやってましたが、それがどうです、
今では百五十円、二百円なんてんですからね、夢ですよ。
そのころ百円札なんか持ってってごらんなさい。あいつ怪しいんじゃねえかなんてうさん
に思われたもんです。ですから寄席の木戸なんかみんなバラ銭で、毎晩ハネると台箱(木戸
で下足札などを積んでおく箱)の上へゼニを三山に分けて積んで、一山を席亭が、一山を真
打が、あとの一山を真打外の出演者がとることになっていました。
大ザッパなもので、それでもすんでいたんですが、今は楽屋と席亭で四分六だ、やれ七三
だ、税がどうの非課税の分がどうのと、世の中のよかったころだけしか知らないわれわれじ
じいはノイローゼってんですか、あれにならないのが不思議なくらいです。
それに昔と今のひどい変わりようは高座数で、昔はどんなに多くても十高座以内で、です
からやる方でもじっくりと芸がやれるし、お客もたんまりたんのうできましたが、それが今
はどうです、二十高座からはなはだしい時は二十二、三高座もあるんですからこれでは芸人
も上がったと思うとすぐ下りなければならないし、お客だって落ちついて聞いちゃいられま
せん。寄席のおやじがそんなこといっちゃ困りますがね…
出演者が多いから高座の約束もつい破らなければならない勘定なんですが、昔は仲入りの
あとは三高座と決まっていました。仲入りがすむとすぐそのあとへ上がるのが”くいつき”
といって、たいていその時のトリの弟子が上がり、その次が”膝(ひざ)代り”といって糸
ものとか百面相とか曲独楽とか籠(かご)まりとか、で最後に真打が上るから真打の芸がぐ
っと引立つというものですが、それが今ではメチャクチャで、仲入り後に数高座あったり、
膝代りに落語を掛合いでやってるようないわゆる素噺漫才が上ったりでは、これでは真打の
芸はまるで引っ立たないというわけで、ですから昔の真打は、小さんは鶴枝、圓右は萬橘、
燕枝は三好、圓蔵は滝五郎、橘之助はむらくというふうに膝代りを専属のようにきめていま
した。
”くいつき”に自分の弟子を使うのはいつも浅いところ(客のそろわない宵のうち)にば
かり出ている弟子を、深いところへ出して売ってやろうという親心からで、また今晩は時間
が伸びているから短か目にやれとか、またゆっくりやれとか、他人には言えないことも弟子
になら言えるからで、どっちにしてもこんなのは昔の習慣に返した方がいいと思います。
写真は曲独楽㊨と「どんつく」の籠まり